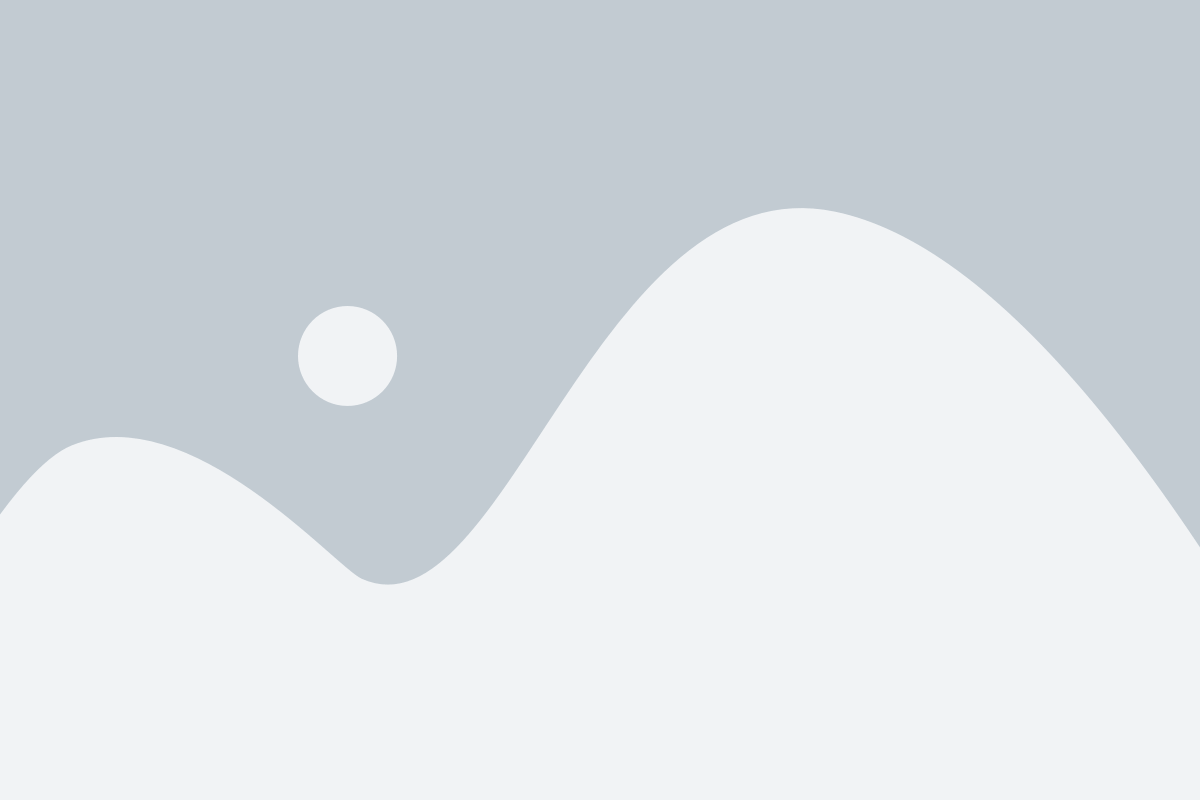第25回|グリーフケアとAI
対話型の生成AI(人工知能)を使ったことはありますか。ChatGPTT(チャットジーピーティー)をはじめ、今やAIは私たちの生活に深く入り込み、私自身もコラムの構想を練る際、AIに相談してみることがあります。1年ほど前までは「とんちんかん」だった回答も、今では驚くほど説得力のある言葉が返ってくるようになりました。
では、私たちのグリーフ、大切な人やもの環境などをうしなったことで心や身体に起こる様々な反応をAIはどのように受け止めてくれるのでしょうか。今、世界では亡くなった人をAIで再現する試みが広がっています。 例えば、故人が生前に書いた文章からその人らしい言い回しを学び「手紙」を届けてくれるサービスや、生前の音声から「声」を再現するもの、さらには動画で故人が語りかけてくるものまで登場しています。
これらは、グリーフケアに役立つのでしょうか。 結論から言えば、その答えはまだ出ていません。AIで故人を再現する事業者を中心に大きな効果を期待する声がある一方で、実際にどのような心理的影響があるかは、まだ研究途上であり、十分に解明されているものではありません。
死者をAIで再現すること自体も、肯定的な意見と否定的な意見の両方が聞こえます。少し古い話ですが2019年の紅白歌合戦でAI美空ひばりが歌ったことを覚えている人もいるでしょうか。あの時も美空ひばりが蘇ったようだと喜ぶ声や、死者への冒涜だと批判的な声など賛否両論がありました。現在の生成AIによる故人の再現も死者の尊厳の問題や、AIで蘇らせる(=再現する)ことでAIに過度に依存してしまうのではないかという懸念も指摘されています。
現在は、多額の費用もかかり、反発も多い故人の再現AIを万人に勧められる状況ではないと思います。私自身も身近な人をAIにより再現することには強い抵抗感があります。それでも、伝えられなかった思いをAIに託すことで、心が軽くなる方がいるのも事実でしょう。急速に進化する技術の波の中で、私たち一人ひとりがそれぞれのグリーフとどのように付き合っていくのか、選択肢は増えているのを感じます。